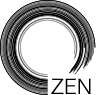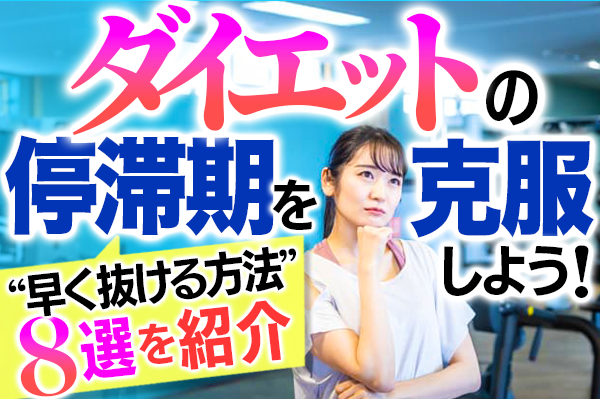ダイエットの停滞期を抜け出すチートデイの正しいやり方と失敗例5選

ダイエットを始めてまもなくは体重が落ちやすいものの、しばらくすると「停滞期」がやってきます。チートデイは、ダイエットに挑戦する誰しもがぶつかる「壁」を乗り越える秘策の一つです。
ダイエット中にあえてカロリーの高い食事を摂る日を作ることで、いったん落ちた代謝を活性化する狙いがあります。
この記事では、ダイエット停滞期におけるチートデイの効果や方法を紹介します。
前半ではおすすめの食材やカロリーの目安、頻度の決め方といった基本的なルール、後半では「チートデイでよくある失敗例」を紹介するので、この記事を最後まで読んでダイエット停滞期を抜け出して、理想のカラダを手に入れましょう!
目次
ダイエットの停滞期にチートデイは有効

ダイエットにおける「チートデイ」は多くの場合、好きなものを食べる日という意味で使われます。
チート(cheat)には英語で「だます」と言う意味があり、ダイエットにおけるさまざまな効果が期待されているのです。
ダイエットにおける食事制限で摂取するカロリーが低くなると、身体は生命維持のために消費エネルギーを少なく抑えます。
徐々に摂取カロリーが低い状態に慣れると、体重は落ちにくくなってしまうでしょう。
大量のカロリーを摂取する日を作ることで、身体がダイエットをしていることに気づかせず、代謝を落とさないのがチートデイの目的です。
チートデイの効果
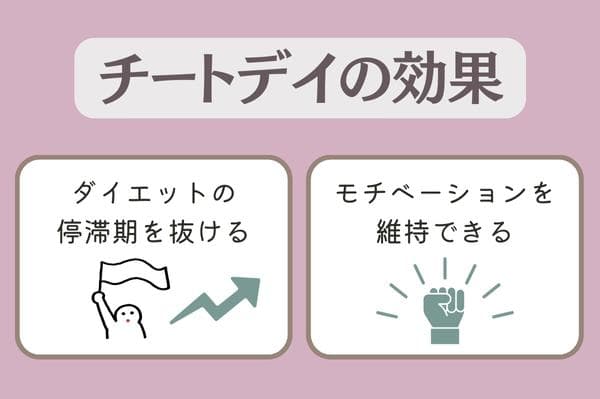
ダイエット停滞期のチートデイに期待される効果は大きく分けて2つあります。
- ダイエット停滞期を抜ける
- モチベーションを維持できる
といった効果について、詳しくみてみましょう。
①ダイエットの停滞期を抜け出せる
ダイエット期間にチートデイをうまく取り入れることで、いったん落ちづらくなった体重を再び減らすことができるようになります。
ダイエットでは食事の量を制限し、摂取カロリーを管理するのが一般的です。
ただ、そこで身体が「生きるために必要なエネルギーを摂取できない」と判断すると、代謝を落とし「省エネモード」に入ってしまいます。
結果、消費できるカロリーが減ってしまい、ダイエットの成果が停滞するのです。
ここでチートデイを設定してたくさんのカロリーを摂取すると、脳を騙して基礎代謝が落ちるのを防いでくれるでしょう。
②ダイエットのモチベーションが維持できる
もう一つのチートデイの効果は、ストレス解消です。
厳しい食事制限が必要なダイエットは肉体的だけでなく、精神的にも辛いですよね。
チートデイには炭水化物や甘いスイーツをたくさん食べられるため、ダイエット期間のストレス発散になるでしょう。
「よし、また明日から頑張ろう」「あと2日でチートデイだ」というように、チートデイはダイエット中のモチベーション維持にも大切な役割を果たしているのです。
チートデイのデメリット

ダイエットには欠かせないチートデイには、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
ここでは3つのチートデイのデメリットを紹介します。
間違ったチートデイは逆効果
ダイエット停滞期を抜け出すには「正しいチートデイ」について知っておく必要があります。
たとえば、以下のようなチートデイは逆効果になる可能性が高いでしょう。
- そもそも停滞期でない
- 摂取カロリーがふだんと変わらない
- 昼にまとめて食べた
- 気づいたら週2回やっていた
- お酒もたくさん飲んだ
間違ったチートデイでは本来の効果は得られず、逆に摂取カロリーが増えるだけになってしまうのです。
記事の中盤で「正しいチートデイのやり方」について紹介するので、チェックしてください。
効果は個人差が大きい
ダイエットの効果には、個人の体質による差が大きく関係しています。
これはチートデイでも同様です。
チートデイを入れてすぐに効果が出る人もいれば、なかなか停滞期から抜け出せない人もいます。
チートデイのやり方が間違っていたり、ふだんのダイエットでの食事制限が不十分なケースもあるでしょう。
あくまで、チートデイの効果には個人差があるものと知っておく必要があります。
食事管理への意識が薄れる
チートデイをきっかけに、それまで続けていた食事制限ができなくなる可能性があります。
いったん食事管理がゆるむと、元の厳しい水準に戻すのは難しいでしょう。
最悪の場合、ダイエット自体をやめてしまう人も出てしまうのです。
チートデイで好きなものを食べた快感が忘れられず、食事管理のモチベーションを失ってしまう恐れがあります。
チートデイは太るだけ?
チートデイを正しくダイエットに取り入れることができれば、ダイエットに効果的なメリットを得ることができます。
チートデイとは、ダイエット中の人が設ける「好きなものを自由に食べられる日」のことです。
チートデイの「チート(cheat)」には、「ズルをする、だます」という意味があります。
痩せるために摂取カロリーを抑え続けていると、体が低カロリーの食事に適応し、エネルギー代謝が落ちてしまいます。
チートデイとして定期的に高カロリーの食事を摂取する日を設定することにより、脳をだまし、ダイエットの停滞を防げるのです。
ダイエット中に糖質や炭水化物をたくさん食べられる日として設定するチートデイですが、正しい方法で行わなければカロリーの過剰摂取により、リバウンドにつながりかねません。
チートデイを取り入れて太るかどうかは、それぞれのダイエット方法や、チートデイの取り入れ方に左右されます。
なので、正しい頻度、正しい方法で上手に取り入れれば太ることはありません。
効果的なやり方

チートデイの効果を最大限発揮するためには、正しいやり方で行う必要があります。
ここでは、チートデイの基本的なルールから摂取カロリーの目安、おすすめの食材などを紹介していきます。
①基本的なやり方
チートデイは、「好きなものを食べていい」というところが強調されがちです。
ただし、チートデイの目的は肝臓にグリコーゲンを貯めることが目的なので、おもに糖質や炭水化物を多く含む食材を食べなければいけません。
仮に、チートデイに「糖質が少なく脂質が多いもの」を食べると、必要なカロリーを得るためには大量の脂肪を摂取することになります。
こうなると、チートデイ本来の効果が失われるだけでなく、脂肪が増えて太ってしまうのです。
②摂取カロリー・糖質量の目安
チートデイの目的は、肝臓にグリコーゲンを蓄えることです。
そのためには、糖質の大量摂取が必要になります。
ここで糖質を中途半端に摂ると、停滞期を抜けられないどころか、逆効果になってしまう可能性もあるのです。
では、糖質の摂取量はどのように計算すればよいのでしょうか。
体重×6グラムを糖質摂取量の目安に
糖質の量を決めるときには「体重×6g(グラム)」を目指すとよいでしょう。
たとえば、体重60kgの人が摂るべき糖質量の目安は「60kg×6=360g」となります。
仮にご飯だけでこの糖質を摂る場合、お茶碗一杯を160g(糖質60g)として6杯分に相当します。
摂取カロリーは基礎代謝の3倍
チートデイに摂取する食事の量を基礎代謝から導く方法もあります。
この場合は「自分の基礎代謝量(kcal)×3」のカロリー量を目安に摂取するとよいでしょう。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」にある「参照体重における基礎代謝量」を参考にすると、日本人男性(30~49歳)の基礎代謝基準値は1530kcal、女性(30~49歳)は1150kcalです。
つまり、男性で4590kcal、女性で3450kcalが、チートデイにおける摂取カロリーの目安になります。
③チートデイに摂るべき栄養素
チートデイには、とくに炭水化物を意識的に摂りましょう。
炭水化物に含まれる糖質を摂ると、食欲を調整するホルモンである「レプチン」を補えるのです。
また、炭水化物を摂取するときには、食物繊維をあわせて摂るとよいでしょう。
食物繊維は糖の吸収を遅らせて、血糖値の急上昇を抑えるはたらきがあります。
チートデイに白米を食べるのもよいのですが、玄米やライ麦パンなどを選ぶと、食物繊維をいっしょに摂れるのでおすすめです。
④チートデイにおすすめの食べもの
チートデイにおすすめの食事を紹介します。
どれも、糖質が高く脂質が低いものばかりなので、好みのものを選んでみてください。
- 寿司
- うどん
- もち
- カレー
- パスタ
- 焼肉
- 丼もの(牛丼、かつ丼)
- ハンバーガー
- フルーツ
- やきいも
- 和菓子
- コーンフレーク
- はちみつ
同じパンでも、ピザパンや菓子パンは脂肪分が多いため太りやすく、たとえチートデイであっても避けるべきです。
チートデイにはかなり大量に食べなければならず「逆に辛い」という声もあります。
まずは、上記のリストの中から自分の好きなものを選んでみて、効率よく糖質を摂取できるようにしましょう。
チートデイの頻度・周期

チートデイを入れるタイミングには「週1回」のように周期を固定するパターンと体温の指標を決めて不定期に入れる方法があります。
また、体重や体脂肪率によっても最適なチートデイの周期は変わるため、詳しく解説します。
- 周期を固定する
- 体温が下がったタイミングで行う
- 体脂肪やBMIから頻度を計算する
①周期を固定する
チートデイの周期を「週1回」「10日に1回」のように固定する方法があります。
わかりやすいのは曜日を固定する方法で、できれば休日に設定するのがおすすめです。
チートデイは1日を通してカロリーを摂取し続けなければならないので、仕事の日に行うのは負担になるからです。
最適な周期は体重やふだんの食事管理によっても変わりますが、多くても週1回までに留めておきましょう。
②体温が下がったタイミングで行う
毎日体温を測定し、0.2~0.3度下がったタイミングでチートデイを入れる方法もあります。
ダイエット中に身体が省エネモードになると基礎代謝が下がり、体温も下がります。
つまり、毎日体温を測定することで、代謝が落ちているかどうかを調べることができるのです。
時間によっても体温は変化するので、できるだけ同じ時間・同じ場所で測定するようにしましょう。
③体脂肪やBMIから頻度を計算する
体脂肪率とチートデイの頻度の関係
チートデイを入れるべき頻度は、体脂肪率によっても変わります。
太っている人は痩せている人よりもチートデイの間隔を狭くするべきでしょう。
ふだんの食事や運動の状況によっても変わりますが、以下の表を参考にしてみてください。
| 体脂肪率 | ||
|---|---|---|
| チートデイの頻度 | 男性 | 女性 |
| 2週に1回 | 20~25% | 30~35% |
| 10日に1回 | 15~20% | 25~30% |
| 週に1回 | ~15% | ~25% |
体脂肪率とチートデイの頻度目安
上記はあくまで目安になります。
自分の生活リズムに合わせて、チートデイを入れるタイミングを調整してみてください。
また、体脂肪率25%以上の男性、35%以上の女性にはチートデイは必要ないとされています。
この場合は、食事管理を徹底する方がダイエット効果は高まるでしょう。
BMIとチートデイの頻度の関係
自宅の体重計が体脂肪率を測れないものの場合は、BMI(Body Mass Index)を使う簡易的な方法もあります。
BMIから算出したチートデイの頻度は以下の通りです。
| BMI | チートデイの頻度 |
|---|---|
| 23~25 | 月1回 |
| 22~23 | 3週に1回 |
| 20~22 | 2週に1回 |
| 18~20 | 週1回 |
BMIとチートデイの頻度目安
※BMIの求め方
BMI=[体重(kg)]÷[身長(m)]÷[身長(m)]
体脂肪の測定ができない場合にはBMIを計算し、上の表を参考にしてチートデイの頻度を決めるのもよいでしょう。
チートデイでよくある失敗例5選

ここでは、間違ったチートデイのパターンを5つ紹介します。
それぞれの失敗への対策も合わせて書いているので、参考にしてくださいね。
チートデイが必要なほどのダイエットをしていない
チートデイのおもな目的は、ダイエットにより落ちた代謝を元に戻すことです。
そもそも、代謝が落ちるほどのダイエットをしていないなら、チートデイを入れる必要はありません。
とくにダイエットを始めてすぐは、食事管理に努めるだけで体重は減っていきます。
本当にチートデイを入れる必要があるのか、チェックしてみましょう。
1食だけの「チートランチ」「チートディナー」どまり
チートデイはその名前にも「デイ」とあるように「1日かけて」大量の糖質を摂取する方法です。
たとえば「ランチだけ」「ディナーだけ」といった食べ方で、一気にカロリー摂取するのはおすすめできません。
一度に大量の糖質を摂ると、血糖値の急上昇をまねき、インスリンが大量に分泌されてしまうのです。
チートデイには、1日かけて、まんべんなくカロリーを摂取しましょう。
- 体重×6(g)の糖質
- 基礎代謝×3(kcal)のカロリー
週に何回もチートデイを入れてしまっている
自分の好きなタイミングでチートデイを入れると、ついついその間隔は狭まってしまいます。
「気づけば週3回もチートデイになっていた」というパターンもあるでしょう。
その結果、カロリー過多となり停滞期から脱出するどころか、逆に太ってしまいます。
チートデイは多くても週1回までにして、それ以外の日にはしっかり食事制限をしましょう。
ダイエット初心者は事前にチートデイを入れる日を決めておき、カレンダーやスケジュール管理アプリなどに書き込んでおくのがおすすめです。
食べる量が中途半端でチートデイになっていない
中途半端なチートデイが逆効果になることもあります。
チートデイの目的は、低カロリー状態に慣れて「省エネモード」に入った身体をもとに戻すことです。
そのためには大量のカロリーを摂取する必要があり、いつもより少し多い程度のカロリーではチートデイの効果は得られません。
中途半端なチートデイは停滞期を抜け出す効果が得られないだけでなく、食欲を刺激してリバウンドの原因になることもあります。
記事の中盤で紹介した「摂取カロリー・糖質量の目安」を参考に、しっかり糖質を摂ることを心がけましょう。
お酒を飲んでしまっている
好きなものを食べていいからといって、いっしょにお酒を飲むのは逆効果です。
アルコールをよく飲む人は脂肪がつきやすく、ビール腹になります。
これはアルコールの摂取により肝臓で中性脂肪が分泌され過ぎた結果、血液中にもれ出てしまうからです。
また、アルコール代謝をしている間は、脂肪をはじめとする他の栄養素がエネルギー源として使われないのも原因の一つです。
たとえチートデイでも、アルコールはできるだけ控えるようにしましょう。
まとめ

チートデイを取り入れることでいったん落ちた代謝を元に戻し、ダイエット停滞期を抜け出すことができます。
間違ったチートデイは逆効果になることもあるので、記事で紹介した摂取カロリーや糖質摂取量の目安、チートデイを入れるタイミングなどを参考にしてみてくださいね。
「チートデイの効果が感じられない」という方は、チートデイの回数やお酒の飲みすぎについても見直してみましょう。